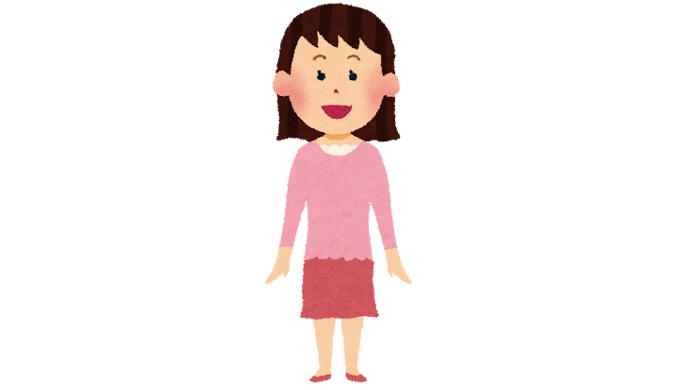近所に住む「むらさきのスカートの女」と呼ばれる女性が気になって仕方のない<わたし>は、彼女と「ともだち」になるために、自分と同じ職場で彼女が働きだすよう誘導する。
(朝日新聞出版公式ページより)

第161回芥川龍之介賞受賞作品。
インターネット・ミームとして有名だが、ニーチェの著作『善悪の彼岸』146節にこんな言葉がある。
“Beware that, when fighting monsters, you yourself do not become a monster… for when you gaze long into the abyss. The abyss gazes also into you.”
「怪物と戦うなら、自身が怪物にならないように気をつけなければならない。あなたが暗い穴の底を熱心に眺めているとき、同時にあなたは底なしの闇にじっと見られているのだ」
必要に迫られて怪物と戦うというのならば仕方ない。だが、やたらと怪物と戦おうとする人間は、すでに半分以上怪物になっているのだろう。普通の人間なら、可能な限り怪物からは遠ざかろうとする。怪物と戦おうというその発想自体が人間のものではない。
同様に、怪物と友達になりたいというのも、怪物の発想だ。深淵を眺めているうちに闇に取り込まれ、自身も怪物となり、結果として怪物と友達になりたいと思う様になるのか、もともと怪物だったのか。
あらすじ
語り手である”わたし”が暮らすアパートの近所には「むらさきのスカートの女」と呼ばれている女が住んでいる。町内では有名で、公園には「むらさきのスカートの女専用シート」と名付けられたベンチまである位だ。
”わたし”はそのむらさきのスカートの女が気になって仕方がない。
むらさきのスカートの女と友達になりたいと思い始めた”わたし”は、どうすれば友達になれるのかを考える。
“いきなり声をかけるのは変だ。“”わたしとしては、まずはちゃんと自己紹介をしたいと思う。それも不自然でない方法で。同じ学校に通う者同士なら、あるいは同じ職場に勤めるものどうしなら、それが可能だと思うのだ。“
かくして、同僚となるため、自らが働く職場に来させようと画策するようになる。話をしたこともない相手を、話をすることもなく誘導することは簡単ではなかったが、無事むらさきのスカートの女と同僚になる。
その後、毎日、話しかけるチャンスを狙って色々と動くのだが、なかなかうまくいかず、結局はこれまでと同様に、遠くから観察するだけの日々が続く。
どういう人と友達になりたいか
語り手の”わたし”は一生懸命、むらさきのスカートの女がいかに変わり者で、町内で有名であるかを熱心に教えてくれる。あんなこともあった、こんなこともあった、だれに似ている、かれに似ていると異常なほどの詳細さで教えてくれる。
確かに、むらさきのスカートの女が少し変わっているというのは”わたし”のお蔭で良く伝わってくるのだが、同時に、”わたし”も変わっていることがどんどん伝わってくる。”わたし”の出してくるエピソードがどれもこれも一般とは感性が違うというか、ピントがずれている。
あくまでも”わたし”の主観のため本当のところはわからないが、”わたし”からみたむらさきのスカートの女は、いわゆるスクールカーストでいうなら最底辺にいるような人物だ。性格は暗く、共感能力も低くて、友達がおらず、何かされても言い返せずただ黙っているだけで、仕事もできないような人物。
そんな人物と情熱をもって友達になりたいと考える”わたし”はどういった人間なのか?
いくら読み進めても”わたし”の私生活が見えてこない。
ただ、見えてこないがゆえに見えてくることもある。むらさきのスカートの女に関して調べることにばかり情熱をそそぎすぎて、私生活と呼べるものがなくなっているんじゃないだろうか、ということだ。
それだけ情熱をそそげば、日常生活に支障をきたしているはずだし、実際支障をきたしているエピソードもいくつかみられるが”わたし”は何も気にするそぶりをみせない。
むらさきのスカートの女が同僚となり、舞台が”わたし”の職場になることで、それまで”わたし”の眼を通してしかわからなかったむらさきのスカートの女のことが第三者の評価という形で伝わってくることになる。それならば同時に”わたし”が第三者からどんな評価をうけているのかもわかってきそうなものだが、その点に関してはほとんどわからないままである。
だれも”わたし”の話をしないし、誰とも絡んでいる様子がないということこそが”わたし”の職場での立ち位置なのか。
謎は深まっていく。
何故、友達になりたいのか
むらさきのスカートの女は、町内で目立ってはいるが、良い意味で目立っているわけではないし、一緒にいて楽しそうな人物ではない。どちらかというと、避けたいような人物だ。しかし、”わたし”は友達になりたいと熱望している。
同じスクールカースト最底辺であることから友達になりたいのか、自分が見下せる人間をそばに置きたいのか、何かに利用したいと思っているのか。
どうやらどれも違う様だ。
同じ職場になり、むらさきのスカートの女が職場に溶け込み、仕事も問題なくこなすようになるのを見ても、友達になりたい気持ちは変わらない。同じだけの情熱で観察は続く。
怪物は誰だ
むらさきのスカートの女をやたらと気にする”わたし”。最初は”わたし”と一緒にむらさきのスカートの女に興味を持つのだが、段々と「この”わたし”は一体何をしているんだ? そもそもこの”わたし”は何者なんだ?」という思いにスライドしていく。
ふと顧みると「この”わたし”は、むらさきのスカートの女を観察して何をしているんだ?」と”わたし”を観察している現実の私がいる。いつの間にか「”わたし”がむらさきのスカートの女にしていること」を「私が”わたし”にしている」のだ。そして、私の書いた感想を読んでいるあなたがいる。
“あなた”は”私”が何者か考えながら、この文章を読んでいるのだろうか?
“あなた”は、”私”が何を考えどういうつもりでこの文章を書いていると思っているのだろうか?
“私”が書いたこの文章を読んでいる”あなた”は何者だ?
観察するものと観察されるものの連鎖で世界はできているのだろうか。だんだんと世界が薄気味悪いものに感じられてくる。

伏線がやたらと仕込まれている。
印象に残るエピソードは、初読み時に「あれは伏線だったのか」と気づけるが、多くは読み返してみて「これは伏線だったのか」と気づく。大した事件は起こらないにもかかわらず、雰囲気だけはサスペンスで、語り手である”わたし”の正体(というほどのことはなにもないが)が徐々にしかわかってこないのも面白かった。
登場人物はだれもかれも好感のもてないような人物ばかりで、明らかな悪意はないものの、自分本位で自分の利益だけを考える人ばかり。ただ、そこが逆に面白かった。どんなひどい目にあっても大して心も痛まないし、ハッピーエンドになろうがなるまいがそんなことは関係なく楽しく感じられる点は、厭らしい人物ばかりが出てくる物語のメリットだ。
楽しくて幸せな話を望む人や、登場人物に感情移入して読むタイプの人にはおすすめできない話だと思う。