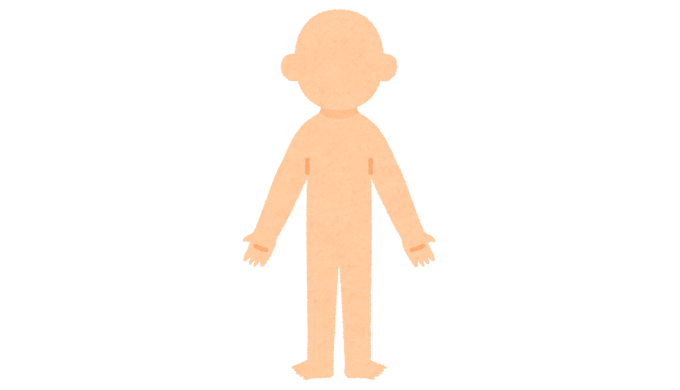夫も食べてもらえると喜ぶと思うんで――死んだ人間を食べる新たな葬式を描く表題作のほか、村田沙耶香自身がセレクトした、脳そのものを揺さぶる12編。文学史上、最も危険な短編集!
「正常は発狂の一種」。何度でも口ずさみたくなる、美しい言葉。――岸本佐知子(翻訳家)
自分の体と心を完全に解体することは出来ないけれど、この作品を読むことは、限りなくそれに近い行為だと思う。――西加奈子(作家)
常識の外に連れ出されて、本質を突きつけられました。最高です。──若林正恭(オードリー)
サヤカ・ムラタは天使のごとく書く。人間のもっともダークな部分から、わたしたちを救い出そうとするかのように。強烈で、異様で、生命感あふれる彼女の作品は、恐ろしい真実を見せてくれる。ふと思うだろう――他の本を読む必要があるのか、と。――ジョン・フリーマン(「フリーマンズ」編集長)
(河出書房新社公式ページより)

表紙には高橋涼子の作品「3つの脳 #4」が使われている。この表紙の作品の主体は三叉の燭台なのだが、その燭台にろうそくは立っておらず、代わりに髪の毛でできた球体が刺さっている。タイトルが「3つの脳」であることから、髪の毛の塊は「中に包まれているであろう脳の象徴」であろう。そして、その脳の象徴が「3つ独立して存在している」ことに意味があるように思う。
いわゆる3つの脳というのは、通常「爬虫類脳」「哺乳類脳」「人間脳」の3つのことを意味する。大体の分け方としてはこうだ。
「爬虫類脳」は脳幹や小脳のように生命維持種族繁栄に関わる脳。
「哺乳類脳」は大脳辺縁系に由来する喜びや怒りのような情動に関わる脳。
「人間脳」は大脳新皮質の働きによるような見聞きしたものを理解し、そこから未来を予測し、予測に対して計画して実行に移すといったような理性に関わる脳。
その「3つの脳」の元となったポール・D・マクリーンが提唱する「脳の三位一体論」は、人間はそれらの3つの脳を進化の過程で順番に獲得していったのだ、という仮説だ。つまり「最初は自らの生命を維持して次世代に繋げていくだけの原始的な生物だったのが、感情を手に入れて、そこからさらに進化し、ついには理性で感情を制御するようにまでなった!」というようなイメージだ。
それが高橋涼子の作品「3つの脳」では、一体化しておらず、全く別個のものとして存在している。この短編集「生命式」には生命維持種族繁栄と感情と理性がバラバラになって、どれを信じていいのかわからなくなっている人達が沢山出てくる。バラバラになるような舞台が用意されていて、「それはバラバラになるな」と納得はするものの「でも、作品内の世界で『バラバラになっていない人』からすれば、こっちの世界こそが『それはバラバラになるな』と思うような世界なのではないか」と考えさせられる。
人体の一部を素材にしたオブジェクトという意味では、この短編集に入っている「素敵な素材」を思わせるが、それだけではなく、この短編集が「生きて繁殖する為に行う行為、動物的とされている行為、人間的と考えられている行為がそれぞれ独立したものなのか、連続したものなのかを問う話」を集めているものであるといった意味もあるのだろうと思う。ちなみに、今はその「脳の三位一体論」仮説は否定されている。生命維持種族繁栄、感情、理性という「わかりやすさ」がうけてか、なんとなくの雰囲気で通説としてそんな風なものがあるように広まっているだけだ。人間の爬虫類脳は本当の爬虫類の脳とは違うし、哺乳類脳も人間以外の哺乳類とは別のものだ。生命維持種族繁栄、感情、理性を司る部位があるにしても、それは全て人間独自のもので、いってみれば全てが人間脳だ。
この否定された仮説が広まっているのは、その「わかりやすさ」ゆえだろう。この短編集の主人公たちは「わかりやすい」ような論を疑い、「わかりやすい」ような論に流されている人たちと部分的に対立してしまう。その対立は、話によって解決したりしなかったりだが、話の結末そのものがどうであれ、「わかりやすさ」ゆえに「脳の三位一体論」に納得してしまう人は、「わかりやすさ」を疑うために、特に読む価値がある一冊ではないかと思う。
あらすじ+α
12の短編が収録された短編集。あらすじに、読んで思ったことをネタバレにならない程度にプラスして紹介する。
生命式
人が死ぬと故人を偲ぶ会が開かれる。それはどの文化圏においても、大体存在する儀式だ。しかしその内容は様々で、日本ではほとんどが火葬だが、「死んでいるとはいえ、人の身体を焼くなんてとんでもない」と土葬をする所もあるし、魂の抜け出た肉体は所詮物質に過ぎないのでこれまで散々他の肉を食べてきたのだから役目を果たした肉塊は自然に返そうと鳥葬を行う所もある。
また、時代によっても葬儀の内容は大きく変わる。同じ日本でも、かつては、故人のためにはたくさんの人に見送られた方が良いという考え方が主流だったが、2000年代に入ると葬儀自体はこじんまりと身内で終わらせ、それとは別にお別れ会のようなものを開く人たちも増えてきた。
同様に倫理観も文化圏、時代によって大きく変わる。「婚前交渉などもってのほかだ」という考えがかつての日本では支配的であったが、今ではない方が珍しいくらいだ。
このように儀式や倫理観というのは、文化や時代によって大きく変わる。それを受け入れられるかどうかは個人次第だ。しかし、ほとんどの人間は少しずつ変遷していく文化に、気付かないうちに慣らされ、昔からそうであったように思う様になる。
さて、生命式である。これは現代日本でいう「お葬式」が変容したもので、故人を偲ぶ点は同じでありながら、その方法として亡くなった人の肉体を食べ、その後、気の合った参加者同士で受精をするという式だ。少子化が極まって、種を増やすことが今よりももっと切羽詰まったものとして目の前に存在する世界で、生命式によって宿った生命は、自分の家庭で育ててもいいし、自分で育てられない場合は専用のセンターに預けてもいい。「増える」ことが重要だから、産みっぱなしで、その後関与しなくても、後ろ指をさされることはない。
そんな世界に生きる一人の女性の苦悩と目覚め。人間の言う「本能」とは一体何なのかを問う作品。
素敵な素材
「3.141592……」とは、言わずとしれた円周率だが、この数字の羅列が「とても人間的だ」と言う人がいる。「動物と比較して人間だけに見られる性質を人間的だと言うなら、『円周率を求める』という行為はとても人間的だということになる。動物は円周率を求めたりはしないのだから」というわけだ。
その考えで行くと、この物語の舞台となる世界はとても人間的な世界ということになる。この話は「もし、人の身体を素材にして物を作る事を是とする世界だったら」というif物語である。タイトルの「素敵な素材」とは、人間の肉体そのもののことなのだ。
同種の生物の死骸を使って自らを飾り立てようという生物はいないだろう。いたとしても非常に珍しいのではないだろうか。だからこそ、それが普通のこととして行われる社会であったなら、それらの行為はとても人間らしい行為として扱われることだろう。
現代では動物の死体の一部を装飾に使ったり、部屋を飾り立てたりするために使うことがある。例えば、毛皮のコートであったり、本革のソファーあったり、壁から突き出るはく製の頭であったりである。それを人間の死体にまで広げた世界だ。
人間の死体を素材にすることに拒否感を覚える登場人物もいて、現実の社会で動物の死体を素材にすることを批判する動物愛護団体に所属するような人々のことが頭をよぎる。だがこの話は「動物の死体を素材にするというのはこういうことだ!」と人間の死体を素材にすることでわからせようというわけでも、そういった人を「動物の死体を素材にすることを批判するのは愚かだ」と批判するわけでもなさそうだ。作者は「どちらにも言い分はあるよね」というフラットな立場をつらぬいている印象を受ける。
村田沙耶香の良いところは、メッセージ性が強いように見える話でありがながら、押し付けがましさがないところだ。
素晴らしい食卓
下手なたとえ話は、話をややこしくするばかりで自己満足に終わることが多い。その点、村田沙耶香の物語はわかりやすい。この話は異文化交流についての話だ。
最近はTwitterのようなSNSが台頭してきて、色んな人が色んな意見を自由に発信することが出来る様になった。それは同時に、自分が発信した意見に対し、誰かによって簡単に反対意見を発信されてしまうということだ。同じ日本人でも、それぞれ様々なバックグラウンドを持っていて、同じ言葉であっても、受け止め方は様々だ。「受け止め方は様々だから気にせず仲良くしよう」とはならず、言い争いに発展することも多い。同じ言語、同じ民族であっても、ちょっとしたバックグラウンドの違いで争いになることを目の当たりにすると異文化交流の難しさを実感する。
この「素晴らしい食卓」で交流することになる文化は、一番身近で多様性がありながら、普段はそれほど対立することがない文化──食文化だ。「普段はそれほどぶつかることがない文化」ではあるが、結婚時や同棲を始めるにあたっては、ぶつかることが多いのも食文化の特徴だ。
この話では、主人公の妹が婚約相手の両親を自宅に招き手料理を披露する。そこで村田沙耶香流の異文化交流を見せてくれる。
起承転結がはっきりしていて短編のお手本のような話だ。作者の言いたいことが本当に読み取れているのかどうかはわからないが、それでも物語としてとても面白い。きっと作者は、説教臭いのが嫌いなのだろう。
純文学のテーマ性とエンターテイメント小説のわかりやすさや面白さが上手く融合していると思う。
夏の夜の口付け
四百字詰め原稿用紙5枚分位の掌編。村田沙耶香の小説によく登場する性的なものを忌避していて、忌避する理由を詮索されるのが嫌いな女性が主人公。性的なものを忌避するとかしないとか問題はそこじゃないんだよ、というような話。
二人家族
「夏の夜の口付け」に出てきた2人と同じ名前の2人が主人公。原稿用紙数枚分位の掌編というところも「夏の夜の口付け」と同じ。同じ名前だが設定が微妙に違うが、二人の会話でその設定が違う理由がなんとなくわかる。
結婚するとかしないとか、誰と一緒に過ごすとかすごさないとか、人生においてそういったことは問題じゃないんだよ、というような話を「夏の夜の口付け」からさらに補強する。
大きな星の時間
掌編。暗くなっても夜にならず、魔法の力で誰も眠らなくてすむ国のお話。
ポチ
中年男性を大人に隠れて飼っている少女二人の物語。
魔法のからだ
心と身体の成長のバランスが身体優位になりがちな思春期において、心の成長を大切にしようとする女の子二人の物語。
心が成長するために知識は糧となる。知識には二種類あって、人から与えられる知識と、自らが体験して得る知識だ。そして、後者の知識しか信用しないタイプの人間がいる。主人公の友人はまさにそういうタイプで、主人公はその友人に触発され、心の成長に必要な知識の素となる体験を得る。
かぜのこいびと
セキュリティブランケットと女の子と女の子の彼氏との三角関係の話。そう書くと彼氏がセキュリティブランケットに嫉妬する話みたいだが、三角の矢印の向きはもっと複雑だ。
パズル
自分の体が自分のものでないようにする感じてしまう瞬間は誰しもあるものだが、それが行き過ぎてしまい自分が無機物にしか思えなくなった女性が主人公の物語。解決の仕方が村田沙耶香。
街を食べる
村田沙耶香にしては、比較的一般的な感覚を持った主人公……かと、思っているとどんどん道を踏み外していく。だが、これまでの主人公とは違い、現代の常識を失わず、しっかりと知識として持ちながら、独自の世界に目覚めていく。
この短編集のこの話までは、独自の世界に目覚めても一人で完結していたり、少人数の仲間内で完結する話がほとんどだが、この話では新たな世界に踏み出そうとする。
孵化
自分の性格がなく、周りがつけたレッテル通りに振る舞ってしまう女性の話。本質的には同作者の『コンビニ人間』と同じテーマと言えるだろうか。コンビニ人間との違いは、コンビニ人間こと古倉恵子は自分に定まった性格がないことについて、ただ「不便だ」としか思っていなかったのに対し、この作品の主人公は「不安だ」と思っている点だ。
「さて、今回はどうやってこの状況を解決するのか?」というのが見所のお話。
最後に

村田沙耶香の主人公たちは、社会に押し付けられた役割に疑問を抱きながら生きていることが多い。舞台となるその「社会」が、現代日本の常識と合致していたりしていなかったりして、読んでいて混乱はするが、それはそれとしてだ。
主人公たちの結末は、社会に取り込まれたり、いいところで折り合いをつけたり、反抗し続けて破滅したりと様々だが、それは村田沙耶香の中で答えがまだ出ないということなのだろうか。それとも、答えが出たからこそ色んなパターンを書いてみているということだろうか。
村田沙耶香の他作品
 『丸の内魔法少女ミラクリーナ』村田沙耶香【ネタバレなし】「確かなものなんてなにもない」ことだけが確かなことだ。
『丸の内魔法少女ミラクリーナ』村田沙耶香【ネタバレなし】「確かなものなんてなにもない」ことだけが確かなことだ。  『コンビニ人間』村田沙耶香【ネタバレなし】本人は言うほど困ってなさそう。
『コンビニ人間』村田沙耶香【ネタバレなし】本人は言うほど困ってなさそう。